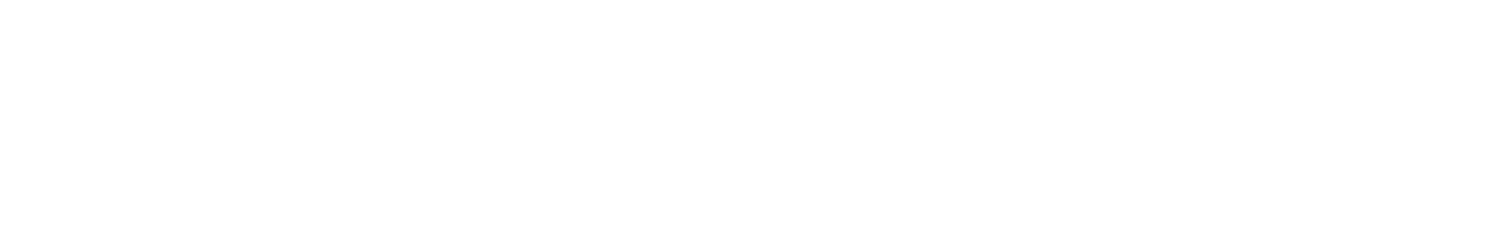長年、小中高生の教育に関わってきた中で子供たちの勉強方法の変化に伴い、廃れた知識としてアルファベットがあります。
「いろはにほへと…」や「睦月、如月、弥生、…」は昔は使われていたけど、今は使われなくなったので、言えないという人はたくさんいると思います。
同じように今はアルファベットを言えない中高生が増えています。
アルファベットが言えない理由としては、辞書を引かなくなったせいだと思っています。
今も英語の授業の最初にどの学校でもアルファベットの順番は教えているはずですが、今の子供たちはスマホで調べ物をするのでアルファベットを使う機会がなく忘れてしまうのだと考えています。
そして、今の若者はテレビもあまり見なくなっています。
情報源はスマホ。
ニュースは見ないという生徒が数多くいます。
今日、何人かの生徒に「ハーバード大がトランプ政権と戦っているの知ってる?」と聞いたら、「知らない」と返ってきました。
「今、お米が高くて問題になっているのは知ってる?」と聞いたら、「それはさすがに知ってます。」とのことでした。
義務教育は、子供たちが社会に出た時に必要な基礎的な資質を養うことを目的としているのだから、米作りが弥生時代に始まったとかよりも、今現在、なぜ米が値上がりして、今後どのようにしていけばよいのかなどの情報を仕入れ、考える力を身につける教育が必要だと感じています。
今現在のことを学ぼうとすると結論のない話が多くなってしまいますが、結論が出ないから無駄とか、教育に適さないということはないと考えます。
考える力を育てる教育にシフトしていくことを強く望みます。