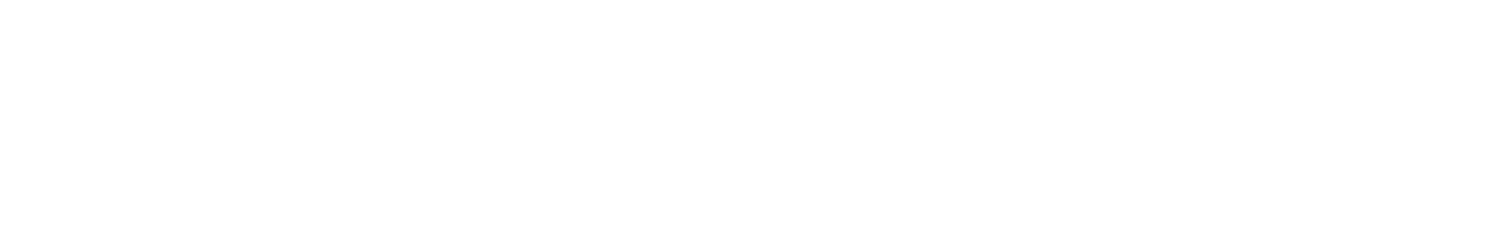中学入試も大学入試も夏~秋ごろに過去問対策が始まります。
過去問対策を始める前には受験校が決まっている必要があります。
(決まっていない場合には、候補の学校も含めて過去問対策を行っていく必要があり、受験生本人の負担が大きくなります。)
進学先は、受験生本人の将来に大きく影響します。
時間をかけて、しっかりと考えていただきたいと思います。
中学入試の場合
受験校を決める上で、学校についてよく知っていただきたいと思います。
- 学校の特徴を知る
私立中学は学校によってさまざまな特徴があります。
宗教、男子校・女子校・共学、部活動の日数、土曜授業の有無、進学実績、2学期制・3学期制、成績不振者に対する対応など - 入試日程、受験科目の確認
中学入試は短期決戦です。
東京・神奈川の場合、2月1日~2月3日の3日間でおよそ9割の試験が行われます。
2月1日、2月2日は午前と午後に試験を受ける受験生が多いですが、多くの学校の試験日程が重なるため、受験できる学校が限られます。
午前試験は4科目の学校が多いです。午後試験は2科目の学校が多いです。 - 出題傾向の確認
募集要項、過去問等に記載されている学校情報などをチェックしてください。
前年度からの変更点などは学校説明会等で説明されることが多いです。
出題傾向は学校により大きく異なります。
国語で記述を多く出す学校、数学で途中式を書かせる学校、社会の歴史は明治以降を中心に出す学校など様々です。
稀に試験の持ち物に定規などの記載がある学校もあります。 - 過去問演習および対策
問題の難易度、時間配分などは実際に受験する本人がやってみる必要があります。
そして、本人は入学試験の対策なんてやったことがないので、対策は保護者様または私たちのような専門家が行う必要があります。
大学受験の場合
大学受験の前には将来どんな仕事をしたいか、大学で何を学びたいかなどの目標が明確になっていることが望まれます。
その上で、大学についてよく知っていただきたいと思います。
学校のことを知った上で、下記のような入試対策が挙げられます。
- 受験方式、受験科目の確認
志望校や志望学部・学科によって試験科目や出題範囲が異なります。
同じ学校の同じ学部でも、学校推薦型選抜や総合型選抜と一般選抜では出題範囲や難易度が全く異なります。 - 英検などの資格の取得
一部の学校では英検などの外部試験を使うことで英語の試験が免除になることがあります。
入試は一発勝負となりますが、英検などの資格は複数回受験ができ、一般入試の点数よりもかなり有利な点数になる場合があります。 - 過去問対策
過去問対策を行う理由としては下記のようなことが挙げられます。
(1) 出題分野・頻出単元を知る
学校によって出題形式は違います。
志望校の出題形式で苦手なものがあったら、練習して得意にすることができます。
例えば、英語なら文法問題は出題されるのか、どのような形式の問題か、
数学は小問なのか、大問なのか、記述かマークか、数学3は出るのか、計算量は多いのかなどです。
(2) 問題の難易度・時間配分を知る
学校によって、合格ラインが65%程度の学校もあれば、80%程度の学校もあり、同じ偏差値帯でも問題の難易度は大きく異なります。
問題にかかる時間も変わってくるので、時間配分なども事前に練習が必要となります。
(3) 対策を行う
学校ごとの傾向を知ったら対策を行います。
学校ごとに特徴的な問題を出す場合にはその対策を行います。
先日、4STEPという数学の問題集を教えていたところ、下記の問題が出題されました。
問題 x>0のとき、次の不等式が成り立つことを示せ。
\(log(x+1)-logx < \frac{1}{x}\)
この問題は微分の単元で出された問題だったのですが、医学部志望の生徒だったので、ついでに東京医科大学で過去に下記のような問題が何度か出されているので、積分を用いた証明も説明しました。
2020東京医科
問題 不等式
\(\sqrt[3]{m+1}-\sqrt[3]{m}<\frac{1}{48}\)
を満たす正の整数mの最小値を求めよ。
2020年の前にこの類題が出されたのが2009年だと思うので、過去何回も出されていると知っているのは私たちのように毎年多くの過去問を解いている人のみだと思いますが、試験本番のわずかな時間でこの問題の解法を考えるのは厳しいと思います。
個別指導で対策をすることでインプットの段階でこのような知識を教えることができたり、過去問対策の際にも過去の傾向を踏まえて「この形式は過去にも出ているからしっかりと押さえるように。」と伝えることができます。